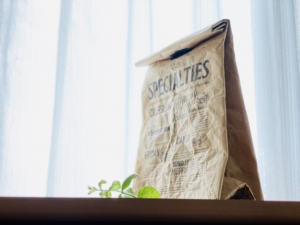みなさんは問診をしたことはありますか?
看護師をしていたら一回はしたことがある人がほとんどだと思います。
「意外と難しいなー」と感じる人も多いかもしれません。
この記事では、クリニック看護師や外来ナース向けに問診の取り方のポイントとコツをまとめてみました!
問診は的確で迅速なケアを行うためにも大切な業務なので、これを体得すると、できるナースにまた一歩近づきますよ。
ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
クリニック看護師の問診って必要?医師の診察だけでいいんじゃない?

問診は患者さんの情報を引き出す大切な第一歩ですね。
また、情報を得るだけでなく患者さんとコミュニケーションをとり信頼関係を築く役割を担っています。
クリニック看護師の問診はスムーズな診察のための大切な仕事になります。
まず、看護師が丁寧な問診を行うことで患者さんの待ち時間が減り、「待ち時間が長すぎる!」といった患者さんの心理的負担も減らすことが期待できます。
そして看護師の問診がしっかりできていると医師が聞き直すことがなく、時間のロスが減り診察もスムーズに行うことができますね。
クリニックの看護師の問診がスピードアップにつながる!

先ほど述べた流れでいくと、看護師がしっかりとした問診を行うことで
- 医師が聞き直す手間が省けスムーズな診療につながる
- 患者さんの回転もスピードアップする
ことができます!
患者さんにとっては病院に費やす時間が減り、早く帰ることができて嬉しいですね。
クリニック看護師や外来の問診や予診のとりかたのコツとポイント

では早速問診のコツを見ていきましょう!
問診票の目的と診療の流れを把握しておく
問診表は何を目的としているのかしっかりと知っておきましょう!
ただ主訴や病歴を聞くだけではありませんよ。
- 普段はどんな生活をしているのか
- 歩けるか
- 麻痺があるのか
- 車いすが必要か
などを把握しておくことで、病院内で安全に診察・診療を受けてもらうことができます。
つまりリスクマネジメントをすることができ、患者さんの利益につながります。
患者さんのS情報とO情報
S情報は患者さんが訴えている内容です。
例えば痛みを訴えているなら
- いつから痛いのか
- 痛みの経過(突然or徐々に痛み出した)
- どのような痛みなのか
- 痛みに変化があるか
など細かく聞きましょう。
私も医師に言われましたが
- 症状はいつからなのか
- きっかけがあったのか
- 症状が出た時と今で変化があるのか
はとても大事だそうです。
次にO情報ですが、これは患者さんを観察して得られた情報です。
例えば
- 足を引きずっている
- ろれつが回っていない
- 顔色が悪い
など沢山得られる情報がありますね。
医師はS情報とO情報を総合して診断、診療を行います。
スムーズな診察と診療のためにも看護師がしっかりと情報を得ておきたいポイントです。
患者さんのニーズを把握することで、どんな検査や処置が行われるか予測ができます。
そうすることで事前準備をしておくことができます。
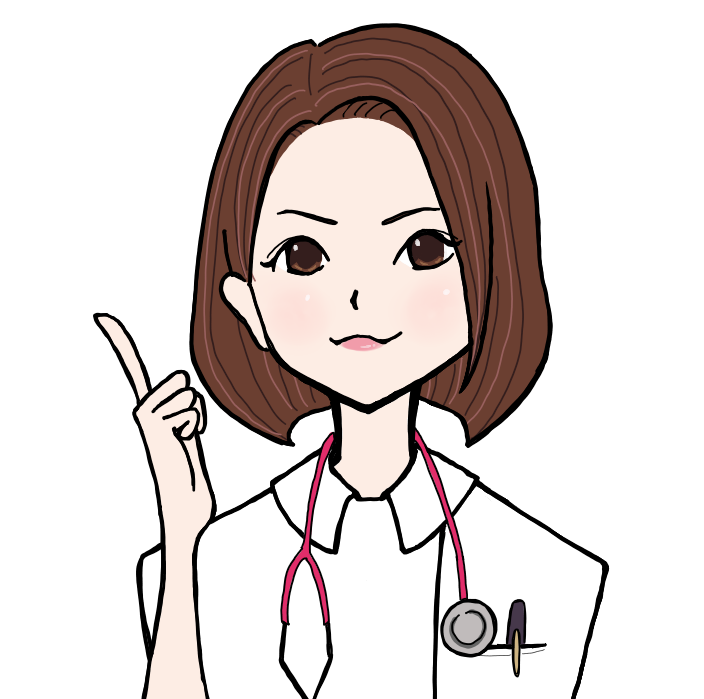 なすこ
なすこさらに診察・診療のスピードアップが図れて患者さんの満足度につながりますよ。
予診や問診で知った内容はスタッフと共有しておく
全スタッフが患者さんのニーズを把握することで事前準備をスムーズにすることができます。
なので、スタッフ間での情報共有が大切です。
電子カルテに事前に記載しておけば、医師やクラークも見ることができますね。
クリニックや外来の看護師が問診で聞くべき7つの項目

問診の際には外せないポイントが7つあります!
意識して必ず確認できるようになりたいですね。
①いつから(発症時期)
いつから症状が出ているのか、これはとても大切です。
例えば
- 今日急に症状が出たのか
- 数日続いているのか
などシチュエーションは様々だと思いますが、急性の症状か慢性の症状かを判断するのに大切です。
②経過(持続しているのか、増強しているのか)
症状が
- 同じように持続しているのか
- 波があるのか
- 増強しているのか
など、診断するのに欠かせない情報です。
③具体的な症状(どんなことがどのように起こっているのか)
例えば頭痛を訴えている患者さんの場合、どんな痛みがどんな状況で発生したか確認しましょう。
- 頭を締め付けられるような痛みが雨が降る日に徐々に発生した
- バッドで殴られたような痛みが突然発生した
などです。
④症状の程度(どのくらい?基準をクリニック内で決めておくと共通認識できる)
一番わかりやすい例はペインスケールですね。
「一番痛いのを10とすると、今はどのくらい痛いのか数字で教えてください」と基準を設けると、スタッフ間で症状の程度を共通認識できます。
また他の例をあげると「風邪の患者さんで座るのも辛い…という場合はベッドルームに案内する」というルールがあればその患者さんを優先的に診察することもできますね。
⑤部位の特定(どこの場所かを実際に手で教えてもらう)
痛みがある場合では、どこが痛いのかを詳しく聞きましょう。
腹痛を訴えている患者さんがいたら
- お腹の上の方が痛いのか
- 下の方が痛いのか
- 左側か
- 右側か
は大事です。
小さい子どもなど、口で言えなくても手で指してもらうといいですね。
⑥楽になる状況や痛くなる状況(どんなときに痛くて楽になるときはどんなときか)
腹痛の場合で考えると
- 食事を摂ったら痛みが酷くなる
- 空腹時の方がラクである
などは診断を下すために必要な情報です。
忘れずに聞いておきましょう!
⑦随伴症状(ほかに気になる情報、自覚症状以外の情報)
主訴以外に何か症状があるか確認しましょう。
腹痛を訴えている場合、吐き気や下痢があるなど随伴症状があるかもしれません。
他にも患者さんが訴えている症状以外にも
- 顔色が悪い
- 目がくぼんでいる
- 唇が乾燥している(脱水症状の兆候がある)
など患者さんをよく診てみましょう。
クリニックや外来の問診で得た情報からできるナースと言われるコツ

せっかく問診をするなら、ただ情報を得ただけで終わらないようにしたいですね。
できるナースというものは先のことまで考えて動くことができる人が多いです。
最初からできる人はいないので、アセスメント力を少しずつ磨いていきましょう!
問診しながら病気にあたりをつけて必要な情報をとっておく
患者さんが訴えている症状から、予測できる病気を考えましょう。
情報量が増えれば病気にあたりをつけられるハズです。
また病気の予想をしながら、有る症状だけを確認するのではなく、無い症状も確認しましょう。
医師が診断をするうえで、無い症状は結構大事になってきます。
次に必要な検査などにあたりを付けて医師に報告
患者さんの症状から、必要な検査を予想することができます。
例えば「胸のレントゲンが必要かも」と思ったら医師に報告し先に準備をしておけば診察後にスムーズにレントゲンを撮ることができます。
そうすることで、患者さんの待ち時間を減らすことができて回転率もあがりますね。
優先度の高い患者がきたときには医師に報告する
例えば、同じ風邪でも人によって重症度が違いますね。
37.2℃の発熱で鼻水が出ている患者さんが先に来ていたとします。
後から40℃近くの発熱で明らかにフラフラしていて座っているのも辛そう…おまけに吐き気も訴えている…なんて患者さんが来たらどちらを優先的に医師に報告しますか?
もちろん後から来た患者さんですよね。
また、この場合は重症の患者さんが何らかの感染症にかかっていることも予想できるので、院内感染を防ぐためにも早めに対処するべきでしょう。
クリニック看護師や外来ナース必見!問診の取り方とできるナースになるコツのまとめ

問診をする時には常にポイントを押さえておきましょう!
- 看護師の問診はスムーズな診察で医師や患者の負担を減らすことが期待できる
- 看護師の的確な問診で患者の回転率が上がることが期待できる
- 看護師の問診や予診のとりかたのコツ
・目的と診療の流れを理解すればリスクマネジメントができる
・患者のS情報とO情報の把握で必要な検査や処置が予測できる
・問診や予診で得た情報はスタッフ間で共有すればスムーズ - 看護師が問診で聞くべき項目
①いつから発症したのか
②今も症状は続いているのか、症状に変化があるか
③具体的にどのような症状か
④症状はどの程度のものか
⑤症状がある詳細な場所
⑥症状がラクになる時があるのか
⑦その他に気になる症状があるのか - できるナースになれるコツ
・問診しながら病気を予測する
・患者の症状から必要な検査を予測する
・優先度の高い患者は医師に報告や院内感染防止の対処
できるナースというものは、常に先のことを考えて仕事をしています。
患者さんの訴えや様子から考えられる病気を予測し、必要になるかもしれない検査を考えておきましょう。
さらに院内で必要な介助(歩行の介助など)も予測し、院内スタッフと情報共有を図ることも大切ですね。
少しずつでよいので実践して、できるナースを目指しましょう!