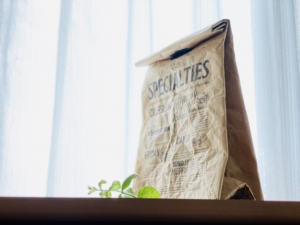学生時代や就職してからも何度も指導を受け、看護師に守秘義務があるということは、看護師であれば知ってますよね。
でも
- 具体的にどういうことに守秘義務があるのか
- どういう場面で守れなくなる可能性があるのか
- 守らなければどうなるのか
わかりにくいですよね。
この記事は、そんな看護師さんに向けて上記の疑問について書いています。
「守秘義務」という言葉だけがやたらと強調されている感じもあり、私も新人看護師の頃は、よく理解しないまま

守らないといけない。
でも何を?どんな風に?
という漠然とした理解でした。
そんな看護師さんに向けて、元看護師、その後大学教員として学生指導を経験した私が解説します。
守秘義務についてどこまでがOKでどこからがNGかを知っておくと、これまで以上に対策をとりやすくなりますよ。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
そもそも看護師に守秘義務があるのはなんで?

看護師に限らずどんな職業でも職務上知り得た秘密を守るという、職業倫理としての守秘義務があります。
その中でも医療従事者など特定の職業につく人には、守秘義務が生じます。
万が一専門職としての秘密保持義務に反した場合は、法律により処罰の対象ともなり得ることとされています。
看護師は、患者の身体的、社会的、経済的情報など、多くの個人情報を取り扱います。
現代では、医学の進歩によって、治療法が複雑化し、治療に関する選択肢も増えました。
そんな中、治療や生活習慣の改善を継続しながら生活していく、慢性疾患患者が増加しています。
- 患者の意思決定を支援すること
- 患者の生活習慣改善のための指導を行うこと
が看護師の重要な役割となっており、そのためには病状だけではなく、患者の生活環境や人間関係など、よりプライバシーや性格に関わる多くの情報が必要とされています。
また、そのような患者を支えるため、チーム医療や、地域および在宅サービスとの連携などが重要となっています。
なので、患者情報が医療機関内にとどまらず、拡大せざるを得ない状況にもあるのです。
そのため、個人情報の保護を一層図っていく必要があり、看護師における守秘義務の重要性はより高まっているといえます。
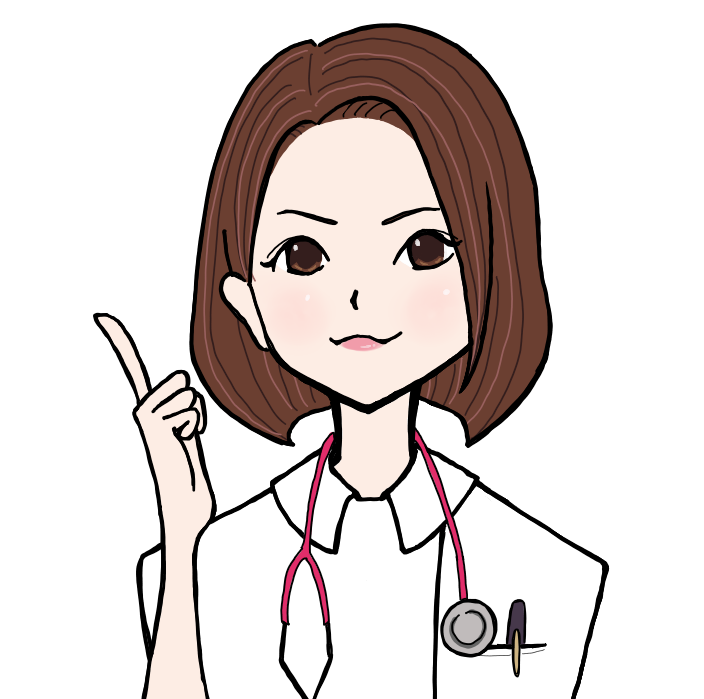 なすこ
なすこ守秘義務が設けられていることで、患者は安心して診療を受けたり、療養することができます。
看護師の守秘義務で患者情報はどこまで言っちゃだめ?

看護師は患者の個人情報を知る機会が多くあります。
これはどこまでならOKというボーダーラインがあるのでしょうか。
個人情報はどこまで言っちゃダメなの?
患者情報は
- 患者の氏名
- 生年月日
- 居住地
- 家族構成などの基礎的情報
- 健康状態
- 病歴
- 症状の経過
- 診断名
- 予後及び治療方針
など、診療記録に記載される内容全てが含まれ、それらは当然守秘義務の対象になります。
診療記録に記載されていないことであっても、その患者に関して知り得たことは患者の個人情報に当たるため他人に漏らすことはあってはいけません。
個人名や病院名を出さなくても、看護師が仕事の内容を話したり、患者の病状を話したりすると、それらの内容を紐づけて、個人が特定できてしまうこともあります。
そのため、患者に関する情報のすべてを口外しないことが必要となるでしょう。
しかし、看護職としてその患者のために、必要な職種間で情報共有を行っていくことは大切なことです。
そのときには必要なコミュニティの中で患者情報を共有します。
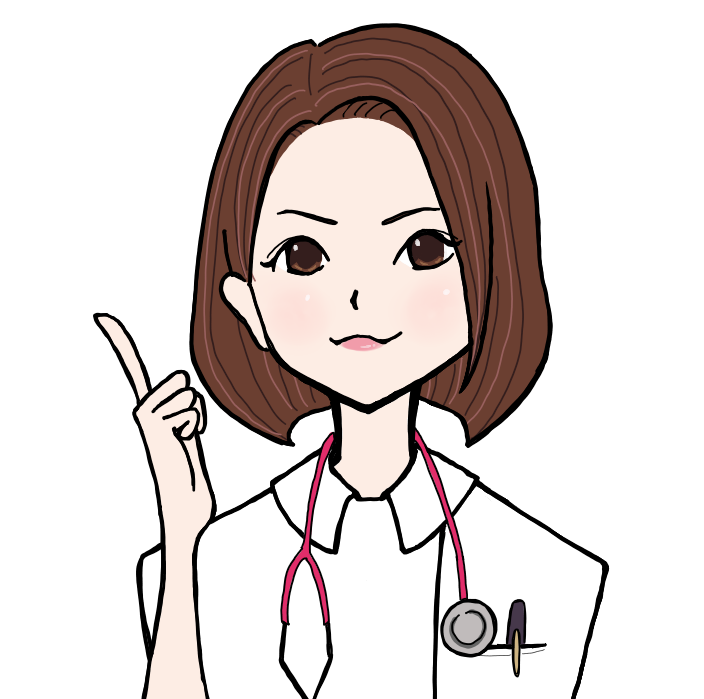 なすこ
なすこ情報共有を行うことにどのような意味や目的があるのかをはっきりさせ、使い方を間違えないようにすることが大切です。
「あなたにだけ話しますね」「誰にも言わないでほしい」と話してくださったことでも
- 看護に必要なこと
- その内容を共有しないことが患者にとって不利益や重大な危険につながる可能性がある
場合には、チーム全体で共有しておく必要がありますね。
亡くなった患者さんの情報なら大丈夫?
個人情報保護法では、個人情報の定義を「生存する個人の情報」としています。
そのため、亡くなった方の個人情報は保護の対象にならないこともあります。
ですが、患者がなくなったからといって急にその情報を雑に扱っていいことにはなりませんよね。
故人の情報が、生前関係していた生存する個人の情報とつながる場合も多いためです。
また地方自治体の保護条例によっては、保護されるべき個人情報について生存することを必須としていないところもあり、取り扱いには注意が必要です。
看護師が守秘義務を守るときにバレやすいシチュエーション

「これくらいなら大丈夫だろう」という気の緩みが、守秘義務を守れていない状況になるパターンもあります。
あなたもうっかりやってしまいがちなシチュエーションがないか振り返ってみましょう。
SNSでのつぶやき
投稿した写真に患者の名前や顔が写りこんでいた場合は、明らかに個人情報の漏洩に当たります。
それ以外にも、仕事の愚痴や悩みを吐き出していたら、内容から投稿者の病院や病棟が特定されることもあります。
そのとき、患者に関することを内容にしていた場合は、患者までもが特定される可能性があります。
具体的に情報を出していないつもりでも、過去の投稿など複数の情報から個人が特定されることに繋がることもあるので注意が必要です。
看護師は、SNS上ではあまり仕事のことについて投稿しないことがベストです。
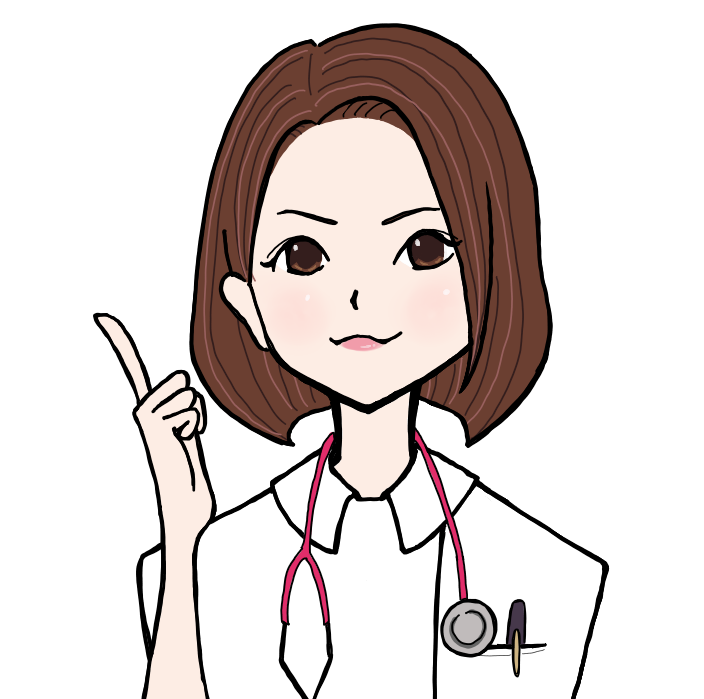 なすこ
なすこですが、投稿する場合には、内容はもちろんのこと、公開する範囲を限定するなどの設定についても気を配る必要がありますね。
同僚との会話
例えば
- 仕事帰りにバスの中や電車の中
- 近くのお店
などで、その日の仕事のことを話していると、その場所や使用している路線などから、勤務している病院や病棟の見当がついたりする場合があります。
特に患者の親族や知人などがいた場合には、話している内容から個人が特定できる場合もあります。
するとその患者がどういう病気でどこの病院に入院しているか、ということがわかってしまうことになります。
患者に必要な看護を検討したり、自分の看護を振り返ったりするために、同僚や上司と患者について話す必要がある場合もあると思います。
しかし、必要な場面で必要な人たちと情報共有するということが大切です。
病院や病棟を一歩出たら、情報漏洩のリスクがあるということを理解した上での行動をとらなければなりません。
看護師が守秘義務を違反すると大変!罰則や処分の内容

ただし、これは守秘義務違反に対する処罰です。
守秘義務違反をして、その被害者や家族のプライバシーを犯し精神的苦痛を与えた場合、被害者や家族が訴訟を起こし、損害賠償に発展する可能性もあります。
その賠償金額においては「いくらまで」と決まっているものではないので、膨大な金額を支払うことになるかもしれません。
看護師の守秘義務はどこまで?周りに話していい内容のボーダーラインを徹底調査のまとめ

- 看護師は患者の病状だけでなくプライバシーも知る立場のため守秘義務を守り情報漏洩をしないことが重要
- 患者に関するあらゆる情報は個人情報として保護されるべきものである
- 患者の死後や自分が退職した後にも守秘義務は継続されなければならない
- 患者をチーム医療で支える職種間での情報共有は必要だが目的を明らかにし必要な範囲でされるべきである
- 看護師が守秘義務に違反した場合には法律によって懲役や罰金が科せられる
- 看護師が守秘義務に違反すれば情報漏洩の被害者への賠償金を支払わなければならない場合がある
患者の個人情報を知る機会が多い立場である以上、患者や職場の人、あなた自身を守るためにも守秘義務は徹底して守りたいですね。
これから、より責任感を持って業務にあたるよう心がけましょう。