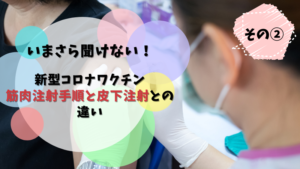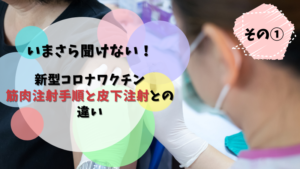日本人の胃がん発生率は世界のトップです。
胃カメラの検査は入院の必要がないことから、健康診断の一環として行われ、クリニックや診療所で行っているところは多いです。
しかしクリニックで働きたいと思っている看護師の方や、子育て中のママ看護師の方にとって
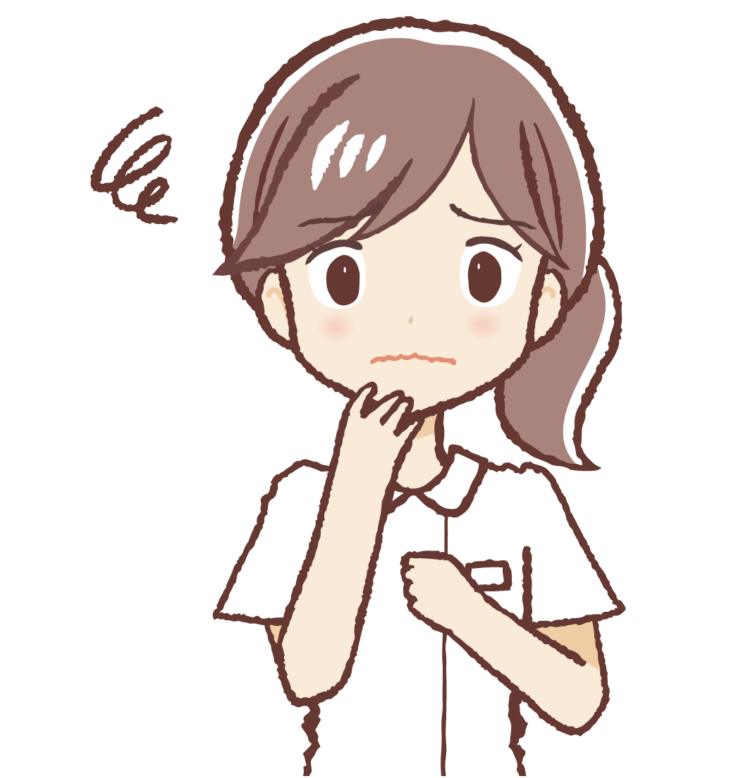
内科のクリニックは内視鏡の介助がいるみたいだけど、自分でもできるかな…
こういった不安から、求人検索をしている時に「内視鏡介助」と記載があるだけで、候補から外してしまうなんてことも。
そんな方に、ここでは胃カメラ(内視鏡)の検査における看護師の仕事内容や介助のコツをご紹介していきます!
この記事を読めば、きっと胃カメラ介助へのハードルが下がりますよ。
ぜひ参考にして、あなたの仕事の幅を広げてくださいね。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の介助はどんなことをするの?どんな人が対象?
胃カメラは医師が行う検査であり、看護師の仕事はそのサポートです。
胃カメラの介助には主にこんな内容があります。
生検
胃の内部に器具を挿入し、胃の壁の一部を採取して検査に出します。
検査の目的は
- ピロリ菌の有無
- がんの有無
を確認する為です。
この時、看護師は指示されたタイミングで医師に器具を渡し、声かけに応じて器具で組織をつまみ、体外へ出す操作を行います。
色素検査の準備
最近はNBI(狭帯域光観察)により、がんの発見がより高まりましたが、がんと正常な胃の境界を見分けるために、色素検査を行うことがあります。
これは、胃の壁に色をつけて、がんと正常な胃の組織の境界を見分ける為に、インジゴカルミンや、酢酸を散布する方法です。
胃カメラを行う患者さんはどんな人が対象?
胃カメラを行う患者さんは
- 胃の不調を訴えることでカメラの検査に進む方
- 健康診断の一環として検査を行う方
がいます。
胃の部位別に、病気を表にまとめました。
| 部位 | 病名 |
| 食道 | 食道がん、食道憩室食道粘膜下腫瘍、食道静脈瘤逆流性食道炎、食道ヘルニア |
| 胃 | 胃がん、胃悪性リンパ腫胃粘膜下腫瘍、胃静脈瘤胃憩室、胃ポリープ胃潰瘍、胃炎、アニサキス症ヘリコバクター・ピロリ菌感染 |
| 十二指腸 | 十二指腸癌、十二指腸潰瘍 |
これらは代表的な病気となりますが、他にも胃の病名はあります。
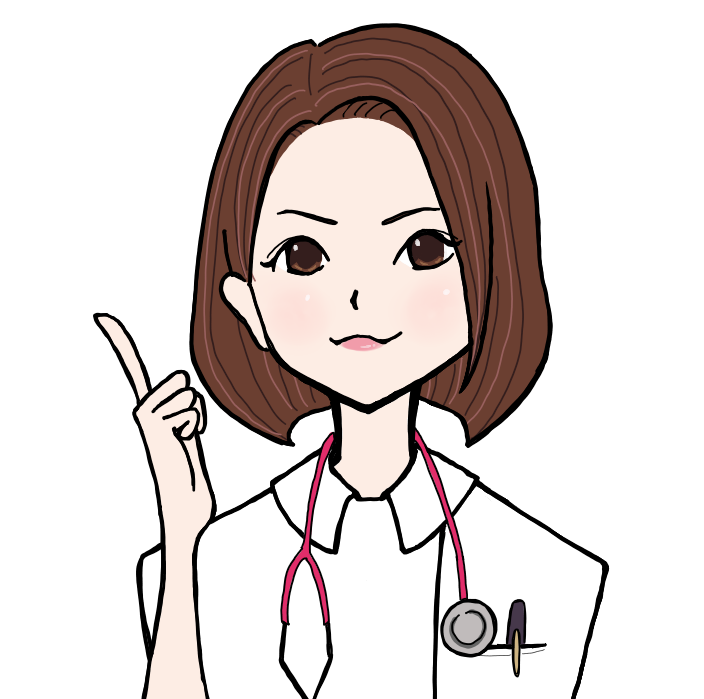 なすこ
なすこ胃カメラを受けることで直接胃の中を観察し、胃の不調の原因や、病気を発見することができます。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)での看護師の仕事内容と役割
胃カメラで、看護師が行なう仕事は、ズバリこの3つです!
それぞれみていきましょう!
患者さんの看護
胃カメラは、医療機関で受ける検査の中で苦痛を伴い、ハードルの高い検査に思われがちです。
そんな患者さんをサポートするのが看護師の役割であり、苦痛を最小限にし、スムーズな検査を行えるかは、準備の段階から大切です。
この為、検査が予定された際には、検査前の準備や生活の仕方など、検査が確実に行えるように入念な説明が行われます。
胃カメラの管理
胃カメラは精密な機械であることから、その取り扱いをしっかりと把握し、検査がスムーズに行える状態にしておかなくてはなりません。
この為、日々の点検や管理といった仕事が重要となります。
胃カメラを管理するには、下記のことを知識として覚えておきましょう。
- 胃カメラの各部の名称や、パーツの種類
- 職場での点検ルール
- 感染症の有無によっての洗浄仕方
医師の介助
胃カメラの検査は医師が行い、看護師はそれを介助をするのが仕事です。
胃カメラ中は
- 患者さんへの声掛けや
- 楽に検査が行えるように背中をさすったり
します。
そして生検などの検査を医師から指示されたり、色素検査を行う場合に、医師の側でその介助を行います。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)でやってはいけないこと
それは、その場所から離れてはいけないことです!
他の検査でも、もちろん言えることですが、理由は二つあります。
それぞれ見ていきましょう。
患者さんの状態が急変することがある為
胃カメラの検査は食事を取らずに行う検査であり、それだけでも
- 血糖値が下がったり
- 脱水状態となり
体調不良を訴える場合があります。
特に、糖尿病や血圧の薬を服用をしている方には、事前の内服の管理や、食事の時間に注意が必要です。
また、胃カメラの検査は、口や鼻からカメラを挿入して行います。
この為、苦痛の多い検査であり、薬を使用して眠った状態で行うことがあります。
これらの薬剤にアレルギー反応が起き、体調が急変することがあります。
検査室には救急カートや、それらに準ずるセットも、事前に用意しておきます。
胃カメラを行なっている医師一人では行えないことがある為
内視鏡室では、医師と看護師の一人ずつで検査を行なうことも少なくありません。
この為、モニターを見ながら胃カメラを扱う医師は操作に集中し、胃の内部を観察していることから、その他の作業を看護師が、サポートしなくてはなりません。
また、患者さんの状態が悪化した時など、医師一人ではその対応が難しく、医師・看護師の連携が必要です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)で必要なもの
必要物品は、以下となります
- 処置用シート(防水シート)
- バスタオル
- ディスポーザブルの手袋
- エプロン
- マスク
- ゴーグル
- 膿盆
- マウスピース
- 2.5ccの注射器
- 23G針
- カテーテルチップ
- サチュレーションモニター
- 血圧計
- 酸素ボンベ・ナザールチューブ
- 内視鏡
必要な薬剤類
- キシロカインビスカス2%(リドカイン塩酸塩液)
- キシロカインスプレー8%(リドカイン噴霧剤)
- キシロカインゼリー(リドカイン塩酸塩ゼリー2%)
医師からの指示された際に準備する薬剤
- ブスコパン(ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg)1A
- 弱ペチロルファン(ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩注射液)1A
- ナロキソン塩酸塩0.2mg 1A
又はアネキセート注射液05.mg(フルマゼニル注射液)1A - 点滴(等張電解質輸液:ラクテックやソルラクトなど)
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の看護手順①前処置

前処置の流れは次の通りです。
- バイタル測定
- 消泡剤を服用
- キシロカインビスカスを含ませ、飲み込まずに5分咽頭にため、時間になったらゆっくりと飲み込んでもらう
- 検査着へ着替え
- セデーション(眠ったような状態で検査を行う)が必要な方には、点滴のラインをとる
- 左側臥位の状態で検査台に横になってもらい、頭の下に処置用シーツ、顔の横に膿盆をセットする
- 血圧計やサチュレーションモニターの装着
- 医師がキシロカインスプレーを咽頭に噴霧した後、マウスピースをくわえてもらう
- 検査開始
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の看護手順②実施中

実施中は声かけやモニターで胃の内部を観察し、医師の指示のもとで必要な処置を介助します。
- 患者さんへ進行状況を伝えたり苦痛がないかを確認
- 適宜、患者さんの背中をさすったりトントンとやさしくタッピングを行う
- バイタル測定を適宜行い数値を確認
- モニターを確認しながら医師から指示された場合は生検や色素検査などの介助を行う
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の看護手順③後片付け

検査が全て終了したら、まず患者さんに声を掛け、検査が終了したことを伝えます。
その際注意がしなくてはならない事は、すぐに動かず、ゆっくりと移動してもらうことです。
これは処置台の高さを上げて検査を行う為、台が高い状態で突然起き上がるのは、転倒の恐れがあり危険だからです。
また、血圧計やサチュレーションモニターなどの装着物もあるため、それらが全て外れてから移動することを伝えます。
更にセデーションを行った方は、薬の効果からふらつきや転倒の恐れがあり、検査後1時間程度、点滴をしながら休んでもらいます。
この時、検査室からの移動を看護師が介助します。
内視鏡自体の片付けは以下となります。
- 画像の出力
パソコンに検査の画像を飛ばす場合、本体の機械を操作し画像を飛ばします。
しかし写真を機械から直接プリントアウトすることもあり、施設によって画像の出力の方法は異なります。 - 本体からカメラを外し洗浄
施設により洗浄方法は異なり
・洗浄機を使用する場合
・洗浄液に浸水させその後手洗いで行う場合
とがあります。 - 洗浄機が終了したらタオル等で拭き上げを行い次の胃カメラの患者さんに備える
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の看護での声掛けのコツ
声掛けを行う場面は以下となります。
それぞれ見ていきましょう。
検査開始前
胃カメラの検査では、口や鼻からカメラを挿入します。
その為、検査中に伝えたいことがある場合には手を少し上げるなど、患者さんと事前に合図を決めておくといいです。
またよだれがでてきますが、咽頭麻酔の影響から飲み込むと咳込んでしまいます。
よだれは飲み込まず、垂れ流すことを伝えておきます。

検査中も側にいますので、何か伝えたいことがある時は合図をしてください。
よだれがでてきますが、咳が出てしまうので、飲み込まないで垂れ流して下さい。
こんな感じで、患者さんに伝えておきましょう。
②検査中
1)開始時
緊張で看護師の声が耳に入りにくい為、なるべくゆっくりとした口調で、丁寧に声を掛けます。

鼻からゆ~っくり吸って、口からゆ~っくり息をはきましょう。
大丈夫ですよ。
2)開始~検査中
緊張で体が固くなると、カメラが入りにくく、更に辛い状況となります!
カメラが進みやすくなるように、直接肩に手を置き、力を抜くように伝えます。

肩の力をぬいていきましょう~。
だら~んと、そうです。
また、目を固くつぶってしまうと力が入る為、できるだけ目は開けてもらうようにします。

目はなるべくつぶらず~、ぼ~っと遠くを見るようにしましょう。
4)げっぷ
胃カメラで空気を送り、胃の内部を観察します。
この為、胃の張った感じがしますが、げっぷを我慢することを伝えます。

げっぷがでそうになりますが、胃の中をよく見ていますので、少しがまんしてください。
げっぷをがまんすると、早く終わりますよ。
5)検査後
検査が終わると安心しすぐに動きたくなってしまいますが、まずは体勢を整え、検査が無事に終わったことを伝えます。

お疲れさまでした。
今マウスピースを外しますので、よだれは飲み込まず、こちらに(膿盆)だしてください。
胃カメラ(内視鏡)の介助のコツを看護師が徹底解説まとめ

- 胃カメラの介助には生検や色素検査の準備がある
- 胃カメラでの看護師の仕事内容は主に
・患者さんの看護
・胃カメラの管理
・医師の介助 - 胃カメラ中は決してその場から離れてはいけない
- 胃カメラで必要な物品や薬剤は基本的なものと医師の指示によるものがある
- 胃カメラは負担の大きな検査なので医師・看護師の連携がとても重要
- 患者さんへの声掛けや事前の準備がとても大切
いかがだったでしょうか?
胃カメラ検査の介助のコツは、流れを把握しておくことです。
これができると、内視鏡も怖くありません!
また胃カメラ自体を看護師は行いませんが、患者さんへの関わり方で、検査が楽にできたと感じる方も多いものです。
あなたのコミュニケーション力やスキルを活かして、胃カメラ(内視鏡)介助の求人にも応募してみてくださいね。
きっと今後のスキルアップに繋がりますよ。