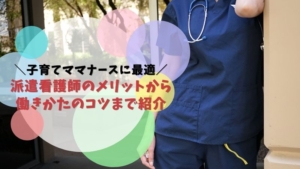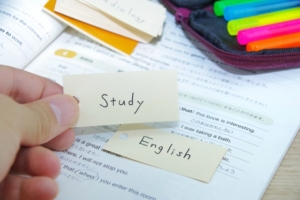妊娠・出産はとても幸せな出来事ですが、看護師として働いていると自分のキャリアがストップしてしまったり、お金の問題など、頭を悩ませてしまうことが沢山ありますよね。
自分が後悔しない選択ができるように、産休・育休制度、失業保険についての知識を活用することはとても大切なことで、自分の看護師人生を大きく左右することにもなるのです。
看護師のパートが産休をもらえる条件

般的に産休とは、出産予定日の6週間前と出産の翌日から8週間取得できる、産前・産後休業のことをいいます。
雇用形態に関係なく、どなたでも取得することができますが、産前・産後それぞれ労働基準法で細かく規定があります。
雇用形態は関係ないのでパートや派遣でも同様です。
まず、産前の休暇は本人が申請した場合のみ、出産予定日の6週間前より取得が可能で、強制的なものではないので、産前ギリギリまで就労を希望する場合はそうすることも可能です。(多胎妊娠の場合は14週から申請することができます。)
しかし、産後の8週間は本人の希望に関わらず就業してはいけないと決まっています。
例外として、産後6週間が経過していれば、本人が就業を希望し、医師が認めた場合のみ就業することができます。
この6週間はどのような理由でも就業できません。
法律で決まっていることなので、違反した場合は罰金や罰則が科せられるため注意しましょう。(妊娠4ヶ月以降は、流産や死産でも出産とみなされるため、同じように休暇が認められることになっています。)
また、産休は勤務期間も関係なく取得できるので、入職してまもなくであっても申請することが可能です。しかし取得することは義務ではないので、希望する場合は必ず申請を忘れないようにしましょう。
産休中にもらえるお金についてですが、
①出産育児一時金は、健康保険加入者か、扶養であれば加入者の配偶者であればだれでも受けとることができ、子供一人につき42万円支給されます。
②出産手当金は、妊婦本人が社会保険に加入していることが条件になります。対象者は産休中に給料の約3分の2が支給されます。
看護師のパートが育児休暇をもらえる基準

育休とは、子供が1歳になるまでの間、男女関係なく取得できる休業制度になります。
しかし、職場復帰予定日までに保育園が決まらず、子供の預け先がない場合など就業が困難な場合は、一定条件を満たせば育休を最大2歳まで延長することができます。
また、育休を1歳6ヶ月まで延長する場合は1歳の誕生日の2週間前まで、2歳まで延長する場合は1歳6ヶ月になる翌日の2週間前までにハローワークに申請が必要になります。
延長申請を忘れてしまうと育児休業給付金をもらうことができないので注意しましょう。
産休は全ての妊娠中の女性に与えられた権利ですが、育休を取得するにはいくつかの条件が必要です。
パートや派遣の場合の条件として、
①同じ勤務先で継続して1年以上勤務していること
②子供が1歳6ヶ月になるまで雇用契約が継続される見込みであること
③週2日以下の勤務や日雇い労働でないこと
育休中にもらえるお金については、
①児童手当は15歳以下の子供を育てる保護者全員が受け取れるものです。
②育児休業給付金は、雇用保険加入者が対象で、育児休業開始日から180日までは休業開始前の給料の67%、181日から育児休業終了日までは50%支給されます。
看護師が産休、育児手当をもらいながら退職しても失業保険はもらえる?

失業保険とは、雇用保険に加入していた労働者が失業した場合、再就職のための求職活動中に国からの給付金が受け取ることのできる制度です。
まず雇用保険は常勤(公務員看護師は除く)であれば必ず加入していますが、パートや派遣の場合でも、
①31日以上の雇用が継続される見込みがある
②1週間の労働時間が20時間以上
以上2つの条件を満たしていれば加入できますので、まずは自分が雇用保険に加入しているか確認しましょう。
看護師はパートでも時給が高いので、扶養内のパートの場合は勤務時間が少なくて雇用保険に加入出来ないことがほとんどです。そのため、扶養内の場合は、出産手当金や育児休業給付金、失業保険は受給することはできません。
また、失業保険をもらうためには、自己都合の退職の場合には、過去2年間で12ヶ月以上、
会社都合の退職の場合には、過去1年で6ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
さらに、失業保険は「就職したくても出来ない失業状態」であることが前提なので、以下の場合は受給することはできません。
①すでに次の就職先が決まっている
②病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに就職することが困難
③しばらく休養したいと思っている
(ハローワークで求人を閲覧したり就職する意思を示す必要があります。)
しかし②の場合は、退職後1年以内に30日以上継続して働けない期間がある場合は、受給の延長申請をすることができます。
失業保険の受給は最大3年間まで延長可能で、働ける状態になった時に申請をすれば受給できます。
失業保険でもらえる金額は、これまでの給料の5~8割程です。
具体的には、退職前6ヶ月分の給料(ボーナスは除く)を180で割った数に給付率(45~80%)を掛けた額です。給付率は給料が高いほど低くなり、もらえる1日あたりの額には上限があります。
もらえる期間は、90~360日で退職した際の年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって決まります。
もちろんその間に再就職先が決まれば給付は受けられなくなります。
妊娠・出産により育休を取得し、職場復帰をする予定だったものの、出産後想像以上に子育てとの両立が困難と感じ、退職を選択することもあると思います。
その場合でも、上記の条件を満たし失業状態であることが認められれば、育休後に退職したとしても失業保険をもらえる可能性は十分にあるのです。その際は育児休業給付金をもらっていたとしても返金の必要はありません。
また、国立・県立・市立病院などの公務員看護師の場合は、雇用保険に加入することができないので、失業保険をもらうことができません。
看護師のパートは育休や産休はとれるの?失業保険も一緒にもらえる?必要な条件と取得するコツのまとめ
産休は雇用形態に関係なく、パートでも誰でも取得できる権利があります。育休、失業保険の制度は、雇用形態や雇用保険、社会保険に加入しているかなど様々な条件によって取得できるのか、給付を受けることができるのか変わってきます。
常勤の場合はほとんどの制度を利用できますが、パートや派遣の場合は、それぞれの制度がどのような条件で利用できるのか、自分がどの条件に当てはまるのかをしっかりと確認することがとても大切です。
あとで後悔することのないように、うまく制度を活用し、看護師としての人生を豊かなものにしていけるといいですね。